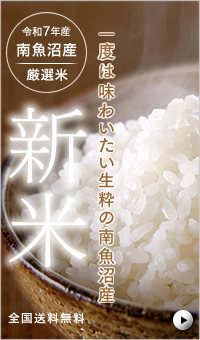毛がになら春の堅ガニっしょ。【北海道枝幸編】
知床斜里を後にして、向かうは枝幸町。
斜里から枝幸までは距離にして240km超。国道238号線をひたすら北上します。

道中、網走市内を通り、サロマ湖を眺めつつ、紋別を過ぎると、目の覚めるようなオホーツクブルーの海が右手に広がります。

 斜里町を出発して4時間半。興部町、雄武町を抜け、ようやく枝幸町に到着しました。
斜里町を出発して4時間半。興部町、雄武町を抜け、ようやく枝幸町に到着しました。
枝幸は毛蟹の漁獲量日本一の町。その毛蟹をアピールするためか、枝幸町の看板には毛蟹が、枝幸のイメージキャラクター「えさっしー君」の帽子にも毛蟹がいます。まさに町総出で毛蟹押し押しです。
流氷明けの3月は毛蟹漁の最盛期。流氷下でじっと身を潜め、流氷が運ぶ豊富なプランクトンを、その身体にたっぷり貯めこんだ毛蟹ガ二。プリプリでたっぷりと身が詰まり、風味も豊かなオホーツクの毛蟹は、春の今が「旬」なのだそうです。
魚屋やスーパーの売り場にも、冷凍ではなく茹でたての毛蟹が当然のようにずらりと並んでいます。
毛蟹一色の街並みを抜け、海沿いにある浜茹で毛蟹の生産者の岡さんを訪ねました。
岡さんのところでは、朝獲れの毛蟹をイケスにも移さず、その日のうちに浜茹で
して出荷しています。
 毛蟹漁は資源保護のため漁獲枠が決められていて、漁獲枠を獲りきったら終了してしまうそうです。今年は漁獲枠が前年に比べて減っている事から、例年より早く終了するのではないかとのことでした。資源量を守る事は徹底されているようです。
毛蟹漁は資源保護のため漁獲枠が決められていて、漁獲枠を獲りきったら終了してしまうそうです。今年は漁獲枠が前年に比べて減っている事から、例年より早く終了するのではないかとのことでした。資源量を守る事は徹底されているようです。
枝幸の毛ガニは型が良く選別もしっかりしているので評価が高いそうです。もともとオホーツク海沿岸の中でも、枝幸は特に毛ガニ資源に恵まれていて、それだけ品質の高い毛ガニを出荷することができるのだそう。
早速浜茹での現場に案内してもらいました。
生きたままボイルすると、生存本能で足を外すので、まずは真水で締め、足折れや身入りの悪いカニを選別してしながら、輪ゴムで足を縛ります。職人さんが手慣れた手つきであっという間に結束する姿はさすが熟練の腕前です。
この検品とゴム止めのスピードでゆでた後の品質が決まるのだとか。
気の抜けない作業です。

 続いて専用の大釜を用いて輪ゴムで縛った毛蟹を高温で一気に茹で上げます。 毛蟹の大きさやその日の温度・湿度などによって、塩加減と茹で時間を微妙に調整するのが職人技。
続いて専用の大釜を用いて輪ゴムで縛った毛蟹を高温で一気に茹で上げます。 毛蟹の大きさやその日の温度・湿度などによって、塩加減と茹で時間を微妙に調整するのが職人技。
岡さんの50年を超える職人としての経験と勘から、グラム単位の塩加減と1秒単位のゆで時間を調整し、絶妙な茹で加減の毛蟹に仕上がります。
茹でたてアツアツの毛蟹を試食させていただきました。殻を外すと、爪の先までぎっしりと身が詰まっていて、ホックホクの甘い身がとてもジューシー。甘みの強さでいえば、越前ガニにも引けを取りません。
「毛蟹食べるんなら、やっぱりミソっしょ。」
と岡さんが、甲羅にたっぷりと詰まった味噌に、ガニと言われる脇腹の身をほぐし和えた状態で差し出してくれました。
一口食べて、あまりの旨さに悶絶!
みずみずしい身質にクリーミーでコクのあるミソの風味が絡み合い、旨みが二乗三乗に増幅されています。
 「うまいっしょ。毛蟹の価値はミソで決まると思うんだよね。蟹は大きいサイズが美味しいっていうけど、毛蟹に関しては俺はそうは思わないのよ。600gを超えるサイズの毛蟹になると、確かにボリュームと迫力はあるけど、ミソの味がちょっと落ちる。それでも他産地の毛蟹に比べればよっぽどうまいと思うけど、俺はやっぱり本当に美味しいミソを食べてもらいたいと思うのさ。」
「うまいっしょ。毛蟹の価値はミソで決まると思うんだよね。蟹は大きいサイズが美味しいっていうけど、毛蟹に関しては俺はそうは思わないのよ。600gを超えるサイズの毛蟹になると、確かにボリュームと迫力はあるけど、ミソの味がちょっと落ちる。それでも他産地の毛蟹に比べればよっぽどうまいと思うけど、俺はやっぱり本当に美味しいミソを食べてもらいたいと思うのさ。」
なるほど。岡さんが大きいサイズをおすすめしない理由がよくわかりました。
「今食べた甲羅に熱燗を注いで、残ったミソを溶かして飲むと絶品なのよ。ちょっと注いでやるから待ってて」
はい、お願いします!と言いかけて、車の運転があったことを思い出し、慌てて辞退させていただきました。
とびっきりの甲羅酒の味を頭の中で妄想?想像しつつ、毛蟹に湧く枝幸を後にしました。